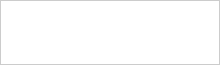●主日礼拝メッセージ(赤文字をクリックするとメッセージが聴けます。MP3ファイル)
マルコの福音書7:1-13 「神の教えと人の教え」 齋藤牧師
【今週のみことば】
「あなたがたは、自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。」(マルコの福音書7:9)
【礼拝メッセージ要旨】
この個所には、弟子たちが手を洗わないでパンを食べていたことを巡っての、パリサイ人たちとイエスのやり取りが描かれています。この出来事を通して、イエスは私たちに何を教えているでしょうか。
1)なぜ手を洗わないのか?
ある時、イエスの弟子たちが「洗っていない手」でパンを食べているのをパリサイ人たちと律法学者たちが見つけて、「なぜ、あなたの弟子たちは、昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚(けが)れた手でパンを食べるのですか。」(5)と言って、イエスを非難しました。当時、ユダヤ人たちは、宗教的な理由から、食事の前に「手を洗う」ことを大事なこととして守り行っていました。その背景には、イスラエルの祭司が幕屋や神殿で奉仕をする時には水で体を洗いきよめなければならない、という神の戒め(律法)がありました。それは一般の民衆には求められてはいないことでしたが、後の時代になって、律法学者たちがこの戒めを拡大解釈し、民の日常生活にまで適用して、食事の前に「手を洗う」ことや、市場から戻ったら水でからだをきよめるとか、食器や寝台までもきよめることが定められていったのです。律法学者たちよって作られたそうした戒めは、人によって作られた「伝統」や「しきたり」となり、「口伝律法」として言い伝えられ、時代を経るごとに付け加えられていきました。そして、イエスの時代には膨大な数となり、人々の生活を縛り付け、重荷となっていました。それでも彼らは、これらを忠実に守り行うように人々に強要し、監視もしていたようです。そして、守れない人たちを「罪人」と呼んで見下していたのです。
2)人間の言い伝えを守っている
それに対してイエスは、イザヤ書のことばを引用し、彼らは「神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを堅く守っている」と言って、彼らの間違いを指摘しました。また、「あなたがたは、自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています」(9)と言って、「コルバン」(神へのささげ物)の例を示されました(10~12)。口伝律法によって、本来の神の戒めがないがしろにされているというのです。
3)パリサイ人たちの間違い
では、パリサイ人や律法学者たちはどこが間違っていたのでしょうか。彼らが見失っていたこととして、3点挙げてみたいと思います。
①まず1点目のことは、彼らは「「形」(形式)にとらわれていた」ということです。彼らは、「昔から教えられてきたこと(伝統やしきたり)」を、そのとおり忠実に守り行うことが、神に喜ばれる立派な信仰なのだと考えていたようです。形(形式)にあまりにもとらわれすぎていたのです。
②2点目のことは、彼らは「律法の本来の意味を見失っていた」ということです。彼らは、神はどうしてこの律法をお与えになったのか、神は何を望んでおられるのか、ということを考えていませんでした。外側だけを一生懸命にきよめて、自分たちはきよくされていると思い込んでいたのです。しかしイエスは、「外側」ではなくて、「内側」(心の中)こそ、きよめられなければならないのだと教えられました。形を守ろうとするあまり、律法の本来の意味を見失っていました。
③そして3点目のことは、彼らは「「ねばならない」という思いにとらわれていた」ということです。どんな組織であっても、人が組織を作り、ルールを定めると、どうしてもそういう意識が働いてくるのかもしれません。「自分の尺度」を人に当てはめて、人をさばいてしまうということもあるように思います。そのように、ユダヤの人々は、「昔の人の言い伝え」をそのまま守り行わなければならない、という思いにとらわれていました。そして、少しでもそこからはみ出る人がいれば、「罪人」と呼んで、交わりから排除するようなことがなされていたのです。
4)イエスが私たちに求めていること
では、この出来事を通して、イエスは私たちに何を教えておられるのでしょうか。これは私たちにも大いに関係のあることであり、私たちも気を付けなければならないことです。具体的に、私たちの個人の信仰生活と、教会生活の2つの面において考えたいと思います。
①まず、個人の信仰生活の面において、例えば、「お酒やタバコ」のことをあまりにも禁欲的に考えて、人をさばくことのないように気を付けたいと思います。また、「仏式の葬儀への関わり」においても、隣人へ哀悼の意を示すことは大切なことです。形にはとらわれないで、そのご遺族のために自分にできることを心を込めてなせればいいのではないでしょうか。そのように、神の教えよりも、人の教えや自分の信念の方が大事になって、人をさばき、自分自身も縛られてしまうことのないように気を付けたいと思います。
②教会生活の面においては、キリスト教会の組織の在り方や礼拝のスタイルも、教会の長い歴史の中で人の手によって形作られてきたものであることを心に留めたいと思います。今の教会のあり方も、人が決めたものであって、昔から受け継がれてきた「伝統としきたり」と言えるのです。そのことを忘れてしまうと、「教会」の組織そのものが神聖化されてしまって、個人の信仰よりも、組織の一員として、教会の伝統やしきたりを守ることが何よりも大事なことになってしまう、ということがあるかもしれません。教会の行事を「守り行う」ことが目的になると、それを行うことの意味を見失ってしまうのです。
また、日曜に教会に行って「礼拝を守る」ということをあまり意識してしまうと、日曜に礼拝を守ってさえいれば自分は大丈夫だとか、立派な信仰者だと思い込んでしまう危険性もあるように思います。日曜だけが特別に大事なのではなくて、むしろ普段の一週間の生活の中で、祈りながら神様との交わりを大切にすることを、イエス様は私たちに求めておられるのではないでしょうか。そのところを見誤ることのないようにしたいと思うのです。
イエス様は私たちに、「形にとらわれ、ねばならないという思いにとらわれて、大事なことを見失ってはいないか」と問いかけておられます。人の教えである「伝統やしきたり」、また「自分の思い」に従うことよりも、まず、神のことば、イエス様は何と言っておられるかということに聞くことを大切にしたいと思います。そのためにも、日々の「みことばと祈りの生活」を大切にしてまいりましょう。